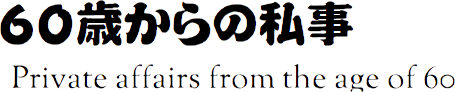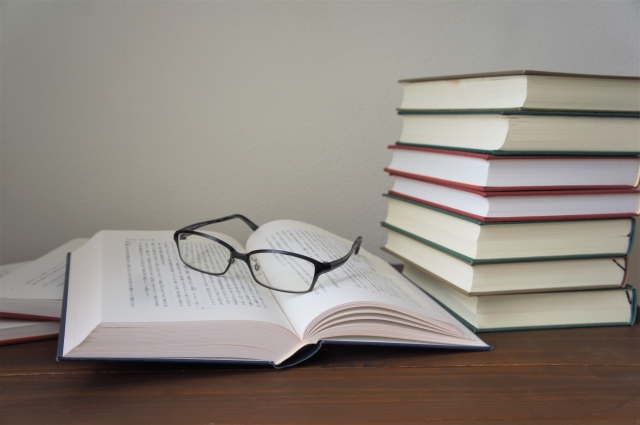第1回「日本ラブストーリー大賞」大賞受賞作であり、原田マハさんのデビュー作。
沖縄の小さな島でくりひろげられる、やさしくて、あったかくて、ちょっと切ないラブストーリーです。
不器用でコンプレックスを抱えた主人公明青(あきお)。初めて本土に旅した際、神社に「嫁に来ないか。幸せにします。」と書いた絵馬を奉納します。その後島に戻った明青のもとに一通の手紙が届きます。「・・・あの絵馬に書いてあったあなたの言葉が本当ならば、私をあなたのお嫁さんにしてくださいますか。・・・」。しばらくすると手紙の差出人幸(さち)が島にやってきます。ここから明青と幸と、裏に住む”おばあ”との不思議であたたかい生活が始まります。
沖縄言葉や風土風習、ページをめくるたびに”沖縄の風”が吹いてきます。今はなき「日本(沖縄)の原風景」なのかも知れません。
今まで私も2度、沖縄を訪れた事があります。南部の戦争跡地や首里城、中部のリゾート観光スポット、そして北部の「やんばるの森」まで。沖縄には様々な顔があります。本土とは全く違った文化は沖縄の宝だと改めて思い知らされました。
作者である原田さんは本作以降、沖縄を舞台にした作品を何作か発表されています。島原産のサトウキビを使ってラム酒を作ろうと奔走する「風のマジム」。そして、本作「カフーを待ちわびて」と同時進行で描かれた、もう一つの物語「花々」。旅好きの原田さんの「沖縄愛」がひしひしと伝わってくる作品です。
沖縄を旅する前、旅した後でも風を感じられる一冊です。