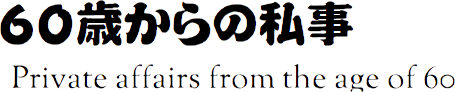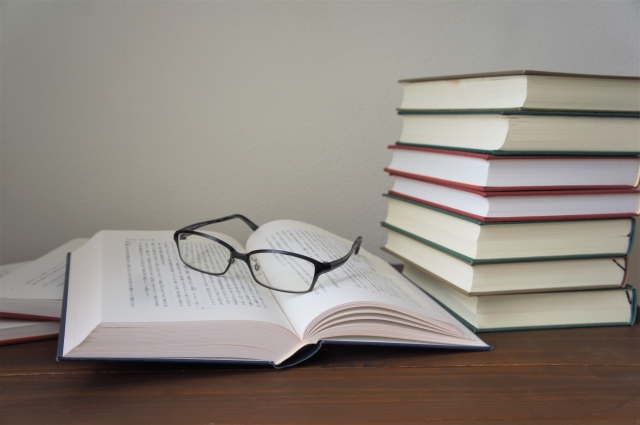”言葉の力”を痛感させられたのが、本書です。
大手製菓会社に勤める二ノ宮こと葉はお気楽なOL。想いを寄せていた幼ななじみの結婚式で、涙が溢れるほど感動する衝撃的な祝辞に出会います。それが、伝説のスピーチライター久遠久美との出会いでした。空気を一変させる祝辞に魅了されたこと葉はすぐに弟子入りし、スピーチライターの世界に飛び込みます。
表紙をめくると”スピーチの極意 十箇条”が紹介されています。ごく当たり前のことなのかも知れませんが、最後の「十.最後まで、決して泣かないこと」は作者原田さんなりのポリシーでもあるのかも知れませんね。
スピーチを通した”人生訓”も描かれています。
・・・聞くことは、話すことよりもずっとエネルギーがいる。だけどその分、話すための勇気を得られるんだ、と思います。・・・
・・・安定した仕事で幸せになるのもいい。けれど、人を感動させ、幸せにする仕事に就けるのはもっといい、・・・
・・・困難に向かい合ったとき、もうだめだ、と思ったとき、想像してみるといい。三時間後の君、涙が止まっている。二十四時間後の君、涙は乾いている。二日後の君、顔を上げている。三日後の君、歩き出している・・・。
本書はもう一つ「政治、政権交代」をテーマとしています。スピーチライターの久美は野党”民衆党”のスピーチライターとして、党幹事長の最後の国会代表質問、弔辞などを手掛けてるのですが、このスピーチシーンが感涙ものです。以前WOWOWにて連続ドラマ化されていてましたが、やはりスピーチシーンは心に沁みましたね。
普通の”お仕事小説”ではない本書は、
・スピーチを生業にしている方(経営者含む)
・披露宴などでスピーチを依頼されている方
そして”議員”さんの教科書になるのではないでしょうか?。