人が死ぬ際に残す珠と噂される「ぎょらん」をめぐる7編の連作集。
ある理由で都市伝説めいたこの珠の真相を調べ続ける、地方都市の葬儀会社に勤める元引きこもり青年・朱鷺を中心として「ぎょらん」にまつわるストーリーを展開していきます。
人生の最後にあらわれる「ぎょらん」を通して、”命に対する贖罪”や”死者への後悔”、そして残された者の”生”への葛藤。
何度も読み返すことでその時々の想いが変わる作品の様な気がします。
各編を読んでいて様々な事を考えさせられる一冊でした。
「ぎょらん」(町田そのこ)
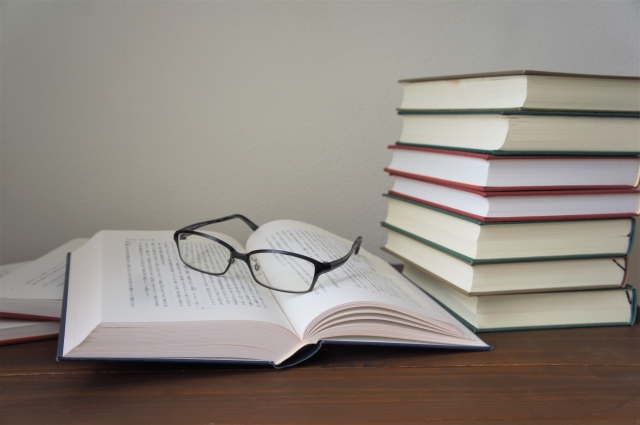
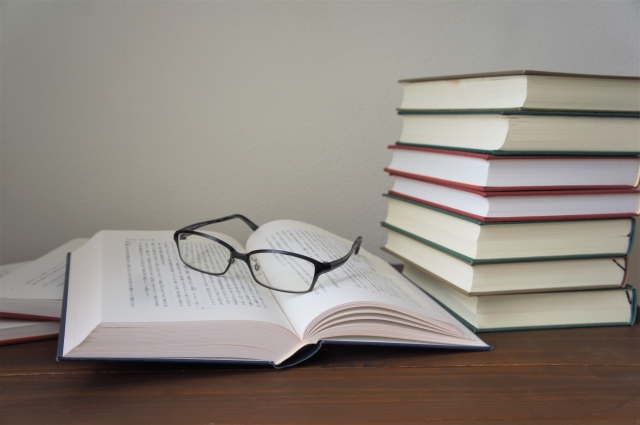
人が死ぬ際に残す珠と噂される「ぎょらん」をめぐる7編の連作集。
ある理由で都市伝説めいたこの珠の真相を調べ続ける、地方都市の葬儀会社に勤める元引きこもり青年・朱鷺を中心として「ぎょらん」にまつわるストーリーを展開していきます。
人生の最後にあらわれる「ぎょらん」を通して、”命に対する贖罪”や”死者への後悔”、そして残された者の”生”への葛藤。
何度も読み返すことでその時々の想いが変わる作品の様な気がします。
各編を読んでいて様々な事を考えさせられる一冊でした。
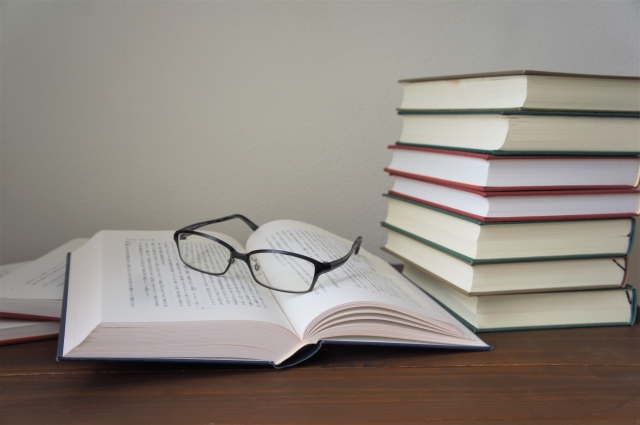
高校卒業直前の街頭インタビューで将来の夢を聞かれたアンちゃんは迷わず「自分のお金でお腹一杯にお菓子を食べる事です!」と答える身長150cm、体重57kg、才能も彼氏も身長もないくせに、贅肉だけは売るほどある18歳の女の子梅本杏子(通称アンちゃん)を主人公とした物語。
高校は卒業したものの、大学へ行くほど勉強は好きじゃないし、専門学校に行くほど好きなことも見つからず、さりとていきなり就職するのもピンとこない。
そんなアンちゃんが働き始めたのがデパ地下の和菓子店「みつ屋」。個性的な店長や同僚に囲まれながら、和菓子の奥深い魅力に目覚めていく、ちょっと変わった”お仕事ミステリー”ですね。
上生菓子から季節の菓子まで「和菓子の歴史」が満載のストーリーは、読んでいて引き込まれますね。今まで触れる事のなかった”日本の食文化”について読みながら考えさせられ、勉強させられました。
文庫化された作品は本作の他に「アンと青春」「アンと愛情」と約一年ごとのアンちゃんの成長が描かれていきます。
アンちゃんが今後どう成長していくのか?楽しみなシリーズになりました。
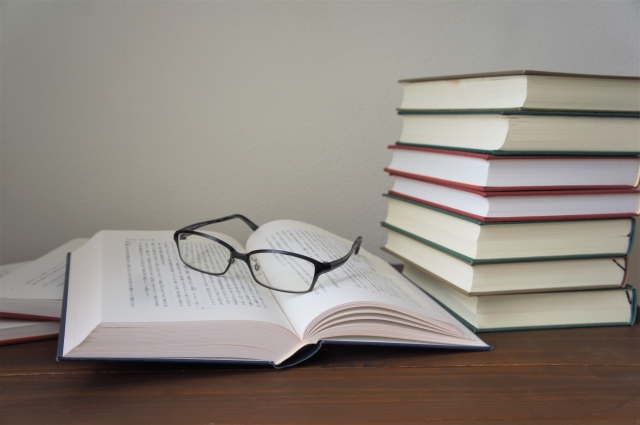
不登校になった息子の父親。
初めての恋に気づく女子大生。
ある秘密を抱える契約社員。
決して交わる事のない3人が繋がっていきます。
テーマは”多様性”。
以前は”個性”とよばれていましたが、”多様性”って言葉がここ数年で市民権を得たんではないでしょうか?。
”個性”は好意的に迎えられてますが、”多様性”はちょっと腫れ物に触る的な印象を感じてます。
文庫本の帯には
「これは共感を呼ぶ傑作か?目を背けたくなる問題作か?」
と書かれていますが、私としては”考えさせられる問題作”に分類したいと思います。
物語としては素晴らしい本なんですが、登場人物達へ感情移入する事が1回読んだだけでは難しかったですね。
何回もじっくり読み返せば、また違った感想になるかも知れません。
私が読書する際は、気になった部分に付箋を貼る事にしているんですが、この本は過去最多の付箋の量となりました。
それだけ消化しきれていないのかも知れませんね。
2023年11月に映画として公開される本作。
https://bitters.co.jp/seiyoku/
監督は「二重生活」「あゝ、荒野」「前科者」と数々の話題作を手掛けて内外から高く評価されている岸監督。
この世界観を2時間程の映像でどう見せてくれるのか?楽しみにしています。
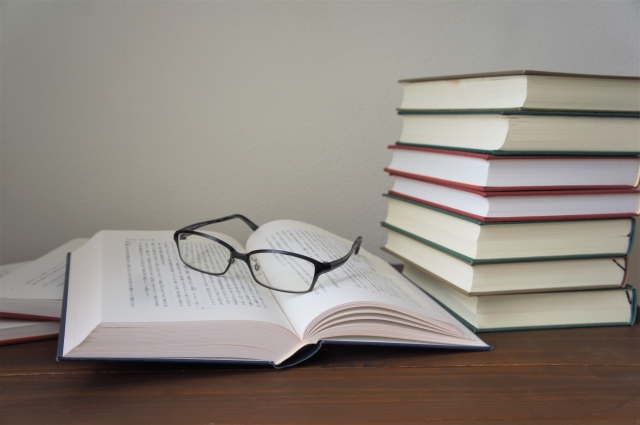
任侠シリーズの第5弾。
出版社、学校、病院、銭湯と再建してきた東京下町人情ヤクザ阿岐本組が、今回はミニシネマ再建に奔走します。
任侠物ってどうしても暴力団同士の抗争や一般人への暴力や嫌がらせなど、血生臭いストーリーになりそうですが、本シリーズは決してそんな展開には持っていきません。最初は見た目や言動で警戒する一般人も次第に親分や組員の人柄や人間性に惹かれていく。
”反社会勢力”と言われる人達を、”反社”の一言で括って欲しくないとあらためて思わされる作品ですが、決して美化したり賞賛する事なく、あたたかい作品に仕上がってますし、ドンパチした抗争もありません。
これまでの「仁侠〇〇」シリーズと多少違うのは、親分と代貸の日村以外はあまり表にでなくなってしまい、子分たちの個性があまり発揮される事はなかったのが残念な点でした。
しかし、”暴対法”の施行や”半クレ”と呼ばれる組織の増殖等、現代社会の問題点を考える意味でも、面白い作品だと思います。
今野さんの作品は「任侠〇〇」シリーズしか読んでいないんですが、他の作品も手に取ってみたくなります。
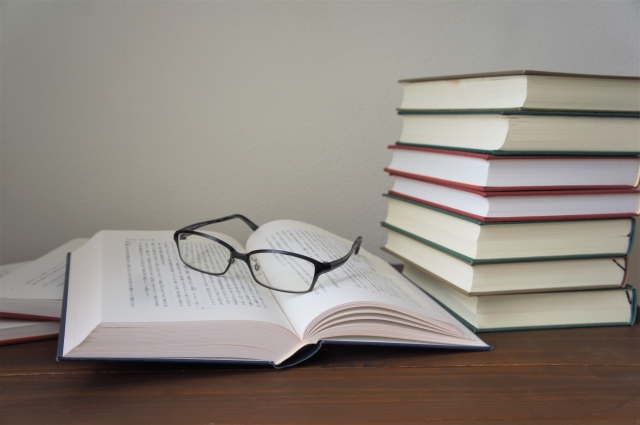
江戸時代末期、姦通の罪を犯した旗本:青山玄蕃。
奉行所は慣例に沿って切腹を渡すが「痛いからいやだ」と言って蝦夷松前藩へ流罪となります。
押送人として19歳の石川乙次郎と一緒に奥州街道を北に進む事になります。
街道沿いで出会った人々と玄蕃と乙次郎の交流。
読み進めていくうちに正直胸が熱くなりました。
江戸末期舞台と言えども、随所に散りばめられている玄蕃の言葉は色あせることなく、今の世でも感銘を受けるに違いありません。
今までも浅田次郎さんの時代劇小説「壬生義士伝」「一路」と読んでますが、本作はどの物語よりも深く胸ぬ迫るものがありますし、あらためて”生きる”って事を考えさせられますね。
本作は出来れば連続ドラマで映像化して欲しい。映画の枠では収まらないはずですから。
しばらく余韻に浸れそうな作品です。
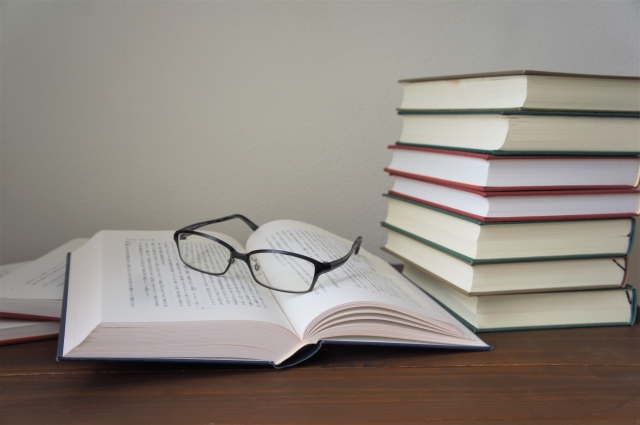
主人公の高林茉莉は二十歳を過ぎたばかり。ひとたび発作に襲われると咳が止まらなくなり、ベットの上でもがき苦しむ。
酸素マスクをしたり外したり、集中治療室と病棟を行ったり来たりの日々が続いている。
院内のインターネットで自身の病状を調べ、余命10年である事を知るところから物語が始まっていきます。
自身の病気に向き合おうとする茉莉の姿には、今までの”病気をテーマとした涙頂戴もの”とは違った作品となっています。
生きている間に何か残そうとする彼女のパワーを感じずにはいられません。
そんな本作ですが、最終章はそれまでとは違った雰囲気となっています。
これが本来の彼女の本音なのかも知れない。
・・・
将来を夢見る力を捨てた
仕事への憧れを捨てた
人と同じ生き方を捨てた
子供を作る希望を捨てた
結婚・恋・愛を捨てた
残ったのは家族だけだ。
それだけは捨てられない。
捨てたくてもこれを捨てたら生きる手立てがなくなってしまうというドライな理由のみで手元に残した。
・・・
生きる意味を、様々な角度から考えさせられた一冊でした。
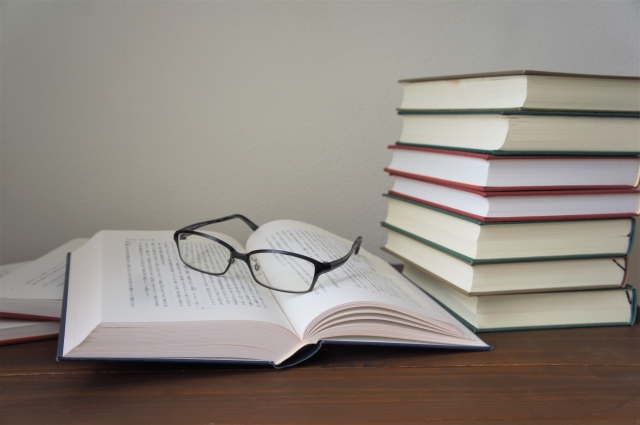
主人公:東山結衣32歳。新卒でIT系企業に就職して10年で中堅として仕事をきっちりこなしつつも、「定時で帰る事」をポリシーとしている。
そんな彼女の奮闘記をテーマとした”お仕事小説”です。
1980年代後半から1990年代にかけての”バブル時代”、「24時間働けますか?」のCMが流行語となった時代。
そのころは24時間とは言わなくても、始発から終電までってのが当たり前だったと時代。
その時代を知ってる”ブラック上司”と結衣と同僚たちの戦いが小気味よく描かれています。
本書で熱血社員として登場する同僚が最後に言います。
・・・仕事っていうのは、もしかしたら、命なんか賭けなくてもできるんじゃないか。そっちのほうがずっとエキサイテイングで、難しくて、挑みがいのあるゲームじゃないかって。・・・
そして結衣の言葉
・・・会社のために自分があるんじゃない、自分のために会社があるんです。・・・
・・・自分のためにならないと思ったら、こんな会社、いつでも辞めていいってことです。会社のために死ぬなんて、馬鹿な考えは起こさないでください。・・・
ブラック上司との最後の戦いは読みながら痛快であり考えさせられました。
今のビジネスマンに共感を得る部分も多いと思いますので、ぜひ読んでいただきたい一冊となります。
あのバブル時代を知っている私たち”ジジイ”が、今の世代に「あの頃は・・・」なんて言ったら完全に袋叩きにあいます。
しかし、あの時代戦ったビジネスマンが居たからこそ、「Made in JAPAN」は確かな技術力として世界に認められた事を忘れてはいけないと思います。
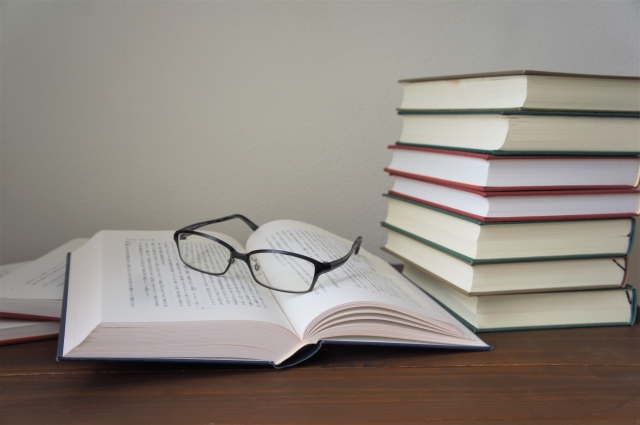
2001年に書籍化された際に手にした本でしたが、20年の時を経て続編が出版された事もあり、あらためて手にしてみました。
水商売(風俗産業)に関する専門教育を行う都立高校を新宿歌舞伎町に設立するところから物語が始まります。
「商業高校は商売を学ぶ子。工業高校は技術を身につけて、工場で働きたい子。農業高校は農業をやりたい子。世の中には水商売ってものがあるんだから、そういう道に進む子の事も考えなきゃならないだろう」
文部科学省のキャリア官僚が酒の席で発した言葉がきっかけで、都立水商が誕生します。そんな突拍子もない高校の3年間が描かれています。
ホステスを養成する「ホステス科」、キャバレーやクラブのウェーイターからマネージャーまでを養成する「マネージャー科」、バーテンダーを養成する「バーテンダー科」。さらにソープランド嬢を養成する「ソープ科」に「ヘルス科」まで。
本作を手に取った時は「色物小説だろう!!」と軽く読み始めたのですが、読み進めると現代の教育の問題点を鋭く切り込んでいく内容に圧倒されました。
「決してあり得ない」設定のフィクションですが、なかなか読みごたえがありました。
初版から20年たった続編「都立水商1年A組」「都立水商2年A組」「都立水商3年A組卒業」の3作は1人の生徒の成長の物語が描かれていきます。
コロナ禍で危機に瀕した水商、性暴力に苦しむ生徒達。いかにして生徒達が”希望”を手にする事が出来るのか?。決して避けては通れない現代が、ここにあるのかも知れません。
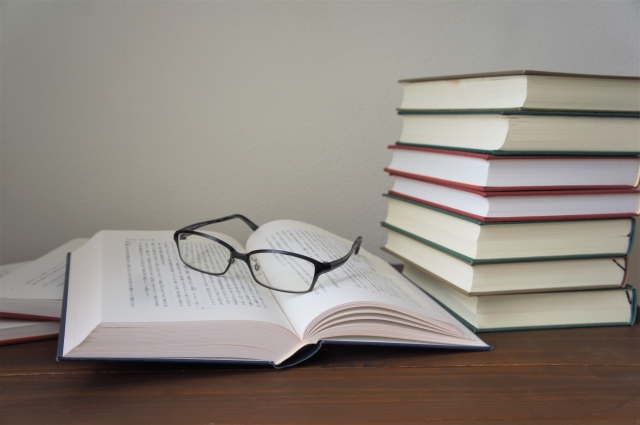
女性客が安心してタクシーに乗れるよう、自分が運転手になると決めた四大卒の新人ドライバー夏子。無賃乗車や強盗未遂などにもあいながら、先輩や同僚そして家族に支えられて、仕事に恋に立ち向かっていく物語です。
小野寺史宜さんの作品は「まち」「ひと」と3作品目の読了となりますが、本作も”人間同士の縁・絆”が優しく繋がっていて、読後あたたかな気持ちになりました。
タクシー業界の内部事情も丁寧に描かれていますので、”お仕事小説”としても楽しめる一冊となっています。
昨年11月には続編「タクジョ!みんなのまち」が刊行されたようですので、こちらも機会あればチェックしたいと思います。
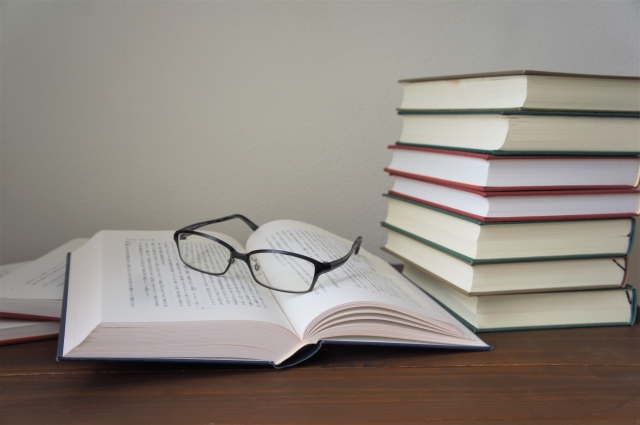
オフィス仲介営業の新入社員の主人公。初契約と思われた案件が押印直前で壊れて、謎の「特務室」に左遷されてからの”反撃?”の物語で、2022年ノベル大賞大賞受賞作。
”仲介業のお仕事小説”としても楽しめますし、ちょっとした謎解きも楽しめる一冊です。
業界のタブーや契約の奪い合い等、読みやすい文体で描かれているので、一気に読み進める事が出来ました。
本作が森ノ薫さんのデビュー作との事ですが、次回作を期待したい作家さんの一人となりました。