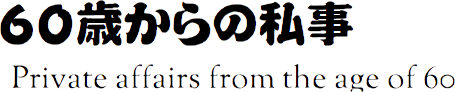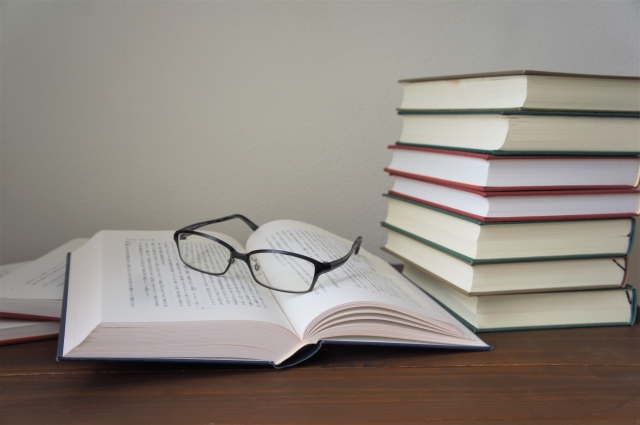夫のDVから逃れるために向かった一軒のシェアハウス?。そこには、幼い頃に捨てられたと思っていた若年性認知症を患った実母と、実母を”ママ”と慕う二人の同居人女性。深い傷を負った主人公が葛藤しながら母娘としての再生していく物語です。
DVの他にも介護やヤングケアラーまで、現在の日本の姿を映し出している作品で、テーマが重いだけに余計に考えさせられました。以前読んだ町田さんの「52ヘルツのクジラたち」「ぎょらん」も”生きづらい社会で耐えながら生きていく”物語でしたが、本作も苦しいながらも優しさに溢れた作品になっていました。
男性である私には理解できない母娘の精神的な繋がりや葛藤を理解出来る訳ではありませんが、”絆”は文章の隅々から溢れかえっていました。もう一度、時間をおいて読み返したい作品でした。
町田さんの作品では「コンビニ兄弟」シリーズも人気ですが、この作品の様な世界観も”町田ワールド”なんだと改めて感じさせられました。