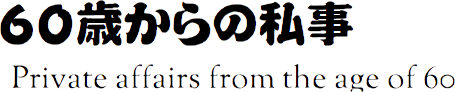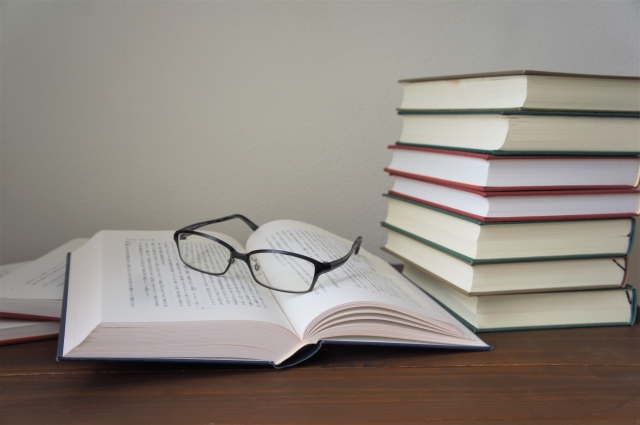両親を亡くし、尾瀬の荷運びを生業とする祖父に育てられた主人公:瞬一。
「よその世界を知れ。知って、人と交われ・・・」とじいちゃんに言われて東京に上京し、隣人やバイト仲間と助け合ったり苦楽を共にしていく物語です。
前作「ひと」からつながる物語との事で、砂町銀座商店街の「おかずの田野倉」も登場します。
東京下町の風景と”人の温かさ”を感じられる作品で、心穏やかに一気に読むことが出来ました。
じっちゃんが尾瀬から瞬一を訪ねてきて話します。
・・・瞬一は頼る側じゃなく、頼られる側でいろ。お前を頼った人は、お前をたすけてもくれるから。たすけてはくれなくても、お前を貶めはしないから・・・
決して器用な生き方ではないかもしれないし、”日に当たらない”生き方かもしれないですけど”人を大事にする”ことが一番と、あらためて痛感させられた一冊でした。